震災遺構 南三陸町防災対策庁舎(2)
公開日:
:
最終更新日:2015/03/27
震災からの復旧・復興, 震災遺構
南三陸町の防災対策庁舎の震災遺構として保存するか否かの問題について、今後の推移について冷静に考察してみようと思います。
1. ボールは町側に投げられて
町長は昨年まで沈黙を守ってきました。
解体を主導する県が、解体を保留したまま、宮城県震災遺構有識者会議を設立し検討を進めている状況が続いていたためと察します。
しかし、2015年1月末に、村井知事が来町し、町長と会合、有識者会議の結果などを踏まえ、20年の県有化し保存する方針を伝えたのです。
『ボールは町に投げかけられた。あらためて検討したい』
会談の場の町役場には町職員遺族ら約30名が詰めかけ、『早期解体を要望します』と書かれた横断幕を掲げ、県知事が到着時には遺族会代表が、県知事に対し嘆願書を手渡しました。
解体を決断した理由である、町の財政負担と復興事業への支障の壁がなくなり、地元の新聞によると、町長の言動に『遺族感情へに配慮』や『解体』がなくなり、『保存の方向に傾いているのではないか?』と受け止められているとのことでした。
南三陸町議会は住民から提出された防災対策庁舎の『県への移譲を求める請願書』を東日本大震災対策特別委員会に付託することを決めましたが、「県の動向を見据え慎重に審査を進めたい。』と2015年3月の定例会では審査を開始せず、以降の定例会に先延ばしにしています。
町議会では2012年9月に、早期解体の陳情を採択した経緯があり、相反する請願書に慎重にならざるを得ない状況のようです。
しかし、県有化受け入れの可否は、防災対策庁舎で助かった町長に決定権があり、県、町議会、住民(遺族会含む)の利害関係が複雑にからみ、難しい決定を強いられていることは確かです。
2.市町村に1つの遺構と経済効果
国(復興庁)は被災した各市町村に1つの震災遺構の保存に向けての初期費用の支援を決めています。
南三陸町の震災遺構候補としては、「破壊力の痕跡」「教 訓」「発信力」「鎮魂」の評価項目において、町内の他の候補とは断トツの違いがあります。
南三陸町の震災遺構候補として町内で断トツなだけではなく、有識者会議の報告書によると、気仙沼市の旧気仙沼向洋高校が『震災遺構として保存する意義が認められる』の評価に対し、南三陸町の防災対策庁舎は『震災遺構として是非保存すべき価値がある』とワンランク上の評価結果なのです。
その評価は他に3施設があり◯印に対し、防災対策庁舎は◎印であり、結論からすると、宮城県で一番残すべき震災遺構候補という報告書なのです。
以上のような評価からは、震災遺構になったとすると、今でも町内外から沢山の方々が訪れ、震災の恐ろしさを知り、弔問してしているのですから、周辺施設含めて、復興公園的な位置づけになれば、広島の原爆ドーム同様の存在価値の可能性が高く、結果的に南三陸町の経済効果に大きく貢献することが安易に想像できます。
3.時間の経過に伴う心境の変化
あるニュースで、防災対策庁舎で犠牲になった町職員のある遺族の心境の変化を紹介していました。
震災当時は見るのも嫌だったが、時間が経つにつれて、向き合って前向きに考えるようになった。
というような心境の変化を紹介していました。
一方で、早期解体を求める遺族会は、行政の進め方に不信感を増し、強固に早期解体を望んでいる姿も見えます。
しかし、これまでの経緯と、力関係と、民主主義の進め方(多数決など)を考慮すると、結論としては、
『震災遺構として保存するために20年間の県有化の棚上げ』
に向かうのではないか!?
というのが一般的な推測になると思います。
でも、それで本当にいいのでしょうか?
立場は違いますが、同じ遺族として、私なりの解決策案を提起したいと思います。
(つづく)
スポンサードリンク
関連記事
-

-
防潮堤問題(3) コンクリート
私たち被災者は、好き好んでコンクリート塀に囲まれるような防潮堤を望んでいるわけではありません。
-

-
住宅再建(2) 自力再建の制約1
住宅再建の早い順の選択項目ごとに、制約条件やメリット・デメリットについて考察したいと思います。 1
-

-
震災遺構 南三陸町防災対策庁舎(3)
石巻市大川小学校の保存の議論 南三陸町の防災対策庁舎を震災遺構として残すか否かの議論の参考になるの
-

-
住宅再建(5) 災害公営住宅での生活再建
体験談初回はこちらから 5. 災害公営住宅に申し込み賃貸にて生活再建 前回は、住民主導型の防災集
-
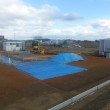
-
住宅再建(1) 震災から5年経過しても
東日本大震災から5年経過しても・・・ 東日本大震災から5年になります。 多分、被災地以外の方
-

-
住宅再建(4) 防災集団移転促進事業(住民主導型)
体験談初回はこちらから 4. 住民主導型の防災集団移転促進事業に参加し住宅建設 本号からは、行政
-

-
住宅再建(6) 遅すぎる住宅再建による変化
体験談初回はこちらから 6. 市主導型の防災集団移転事業に参加し住宅建設 前回に引き続き、もう一
-

-
被災地への旅行についての考察
被災地への旅行者の本心!? 震災から5年になろうとしています。 被災地で宿泊施設(コテージ)を開
-

-
震災遺構 南三陸町防災対策庁舎(1)
『6mの津浪がきます。避難してください!』 南三陸町の職員で危機管理課に所属し、防災放送担当だ
-

-
長引く避難生活における様々な判断(住宅再建)
住宅再建のための的確な判断とは 今回の西日本の洪水・土砂災害と東日本大震災において、広範的な被害と
スポンサードリンク
- PREV
- 震災遺構 南三陸町防災対策庁舎(1)
- NEXT
- 震災遺構 南三陸町防災対策庁舎(3)


