長引く避難生活における様々な判断(一次避難)
公開日:
:
最終更新日:2018/08/09
震災からの復旧・復興
西日本の災害と東日本大震災の共通点
西日本の洪水・土砂災害と東日本大震災(大津波)の共通点として、
- 被害が広範に広がっている。
- 行政の復旧・復興に向けてのマンパワー不足。
- 全壊、大規模半壊が多い。
- ライフラインや交通インフラの復旧の見通しが遅い。
以上のような共通点からは、東日本大震災と同様に、被災者の生活再建には相当の期間がかかることが推測されます。
その結果、ストレスやあきらめ感情などから体調をくずしたり、やる気が失われたりすることが懸念されます。
今後の避難生活や生活再建までに、様々な判断が必要になり、その判断次第で、生活再建が早まったり、遅くなってしまったりします。
東日本大震災の被災経験者として、参考にしてもらいたい情報を提供したいと思いますので、少しでもお役に立てれば幸いです。
一次避難生活の留意点
公共施設などでの一次避難生活
震災発生直後の避難生活の選択肢として、
- 行政施設(学校の体育館、公民館などの公共施設)での集団避難生活
- 被災した自宅(2階が無事など)で避難生活
- 兄弟や親戚を頼っての避難生活
- その他(勤務先などで避難生活)
などが考えられます。
私の場合は工場再建の任務があったことから、勤務先での避難生活と、一般的な一次避難先ではありませんでした。
私が思うことは、酷暑の中、辛い環境のところもあると思いますが、一番良い選択肢は行政施設での集団避難生活だと思います。
理由は、
- 行政や国民の寄付などによるハード綿(特に衣食住)の支援を受けることが出来る。
- 生活再建のための情報収集が容易にできる。
- コミュニケーションを図り、被災した近所みんなで励まし合いながら、協力し合いながら避難生活ができる。
注意点として
- ずうっと集団にいる必要はなく、時々、プライベート的な時間を意識して作る。
- 自己中心的な感情は極力抑え、集団生活での衝突を防ぐようにする。
集団避難生活はストレスそのものです。
従って、時々、息抜きが絶対に必要です。
日帰り温泉に行ってゆっくりするとか、兄弟、親戚のところに行って色々と相談してみるとか、車が無事であれば、夜はエコノミー症候群や熱中症に気をつけて、駐車場の車内で就寝することも有です。
いびきで寝られないとか、いびきをしてしまい周囲に迷惑をかけるとかもストレスになります。
また、中には自己中心的な考え、行動にてトラブルメーカーになる方もいないとは限りません。
極力、協同体制でのルールをみんなで守っていく必要があります。
なるべく、気の知れたご近所が行政区単位でのグループピングとか考慮すべきです。
とにかく、被災者は大きな財産を失いました。
その後の生活再建にも、相当のお金がかかります。
避難生活は行政や国民の支援を遠慮なく受けるべきで、そのためには行政に近いところでの避難が最適です。
兄弟や親戚を頼っての避難生活
一次避難で避けた方が良いのは、兄弟や親戚を頼っての避難生活です。
長期になればなるほど避けた方が良いです。
兄弟と言っても、例えば配偶者がいれば血のつながっていない人もいるのです。また、男女、年齢差などにより、親戚家族が全て同じように、助けよう、支援しよう、となれば良いのですが、中々、いろいろな考えが交錯する可能性が高いです。
避難生活が長期になればなるほど、変化していく可能性が高いのです。
また、同じ屋根の中で生活するとなると、当然ながら生活するためのお金が必要になります。
その負担をどうするのかも切実な問題として意見が合わない可能性が高いのです。
例えば、兄弟・親戚の家に離れとか生活が別々にできる空間があっての避難生活なら別ですが・・・。
被災した自宅での避難生活
次に、自宅な残って、1階は被災したけど、2階が無事だったので2階に避難しているケースがあると思います。
東日本大震災でもそのような被災者は多くいました。
このような場合でも、初期の段階は公共施設などでの共同避難を行った方が良いです。
避難先から自宅に通いながら泥出しや修繕作業を行って良いのです!
時々、自宅で就寝しプライベートを守る時間も必要です。
長期になると、行政の支援がと届きずらく、見放されたような錯覚に陥るケースが実際にありました。
基本は全壊などの人と一緒に避難し、ライフラインの復旧や修繕の進捗などを考慮し、ここからは支援なくても大丈夫!と判断できた時点で自宅に戻れば良いと思います。
一次避難のまとめ
災害直後の被災者は、多くの財産を失い、中には私のように家族・親族を失う方もいて、精神的ダメージが大きすぎます。
そういう時こそ、同じ処遇にあった方々が一緒になって、励ましあって、行政や国民の支援を受けながら、少しづつでもダメージを修復できるような環境にいることが非常に大事です。
自己中心的な行動や人間関係の悪化など、更にダメージを深刻化することだけは避け、被災者だって、時にはストレス解消のために遊んだり、休息をとったり、プライベートな所も大事にし、次へのステップの充電期間になってもらいたいのです。
スポンサードリンク
関連記事
-
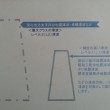
-
防潮堤問題(1) 防潮堤の高さ
東日本大震災の復興事業において、議論、話題になっているのが防潮堤の高さの問題です。 安倍総理大
-

-
震災遺構 気仙沼市のケース
気仙沼市の震災遺構としては、私の目の前に存在している被災した旧気仙沼向洋高校の校舎にすんなり決まりそ
-

-
震災遺構 南三陸町防災対策庁舎は県有化に!
震災遺構として保存の是非で町が二分していた問題ですが、2015年6月30日、南三陸町町長が県の県有化
-

-
住宅再建(3) 自力再建の制約2
体験談初回はこちらから 3. 被災地内外で危険区域以外の土地を確保し住宅建設 前号では、被災地内
-

-
震災遺構 南三陸町防災対策庁舎(3)
石巻市大川小学校の保存の議論 南三陸町の防災対策庁舎を震災遺構として残すか否かの議論の参考になるの
-

-
住宅再建(5) 災害公営住宅での生活再建
体験談初回はこちらから 5. 災害公営住宅に申し込み賃貸にて生活再建 前回は、住民主導型の防災集
-

-
住宅再建(2) 自力再建の制約1
住宅再建の早い順の選択項目ごとに、制約条件やメリット・デメリットについて考察したいと思います。 1
-

-
住宅再建(6) 遅すぎる住宅再建による変化
体験談初回はこちらから 6. 市主導型の防災集団移転事業に参加し住宅建設 前回に引き続き、もう一
-

-
長引く避難生活における様々な判断(住宅再建)
住宅再建のための的確な判断とは 今回の西日本の洪水・土砂災害と東日本大震災において、広範的な被害と
-

-
震災遺構 南三陸町防災対策庁舎(2)
南三陸町の防災対策庁舎の震災遺構として保存するか否かの問題について、今後の推移について冷静に考察して


